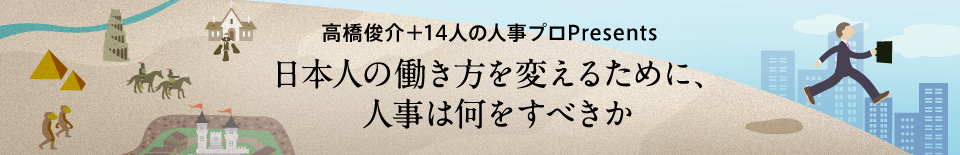
組織人事の世界観ゼミ 課題図書10冊
「世界をどのようなフレームで見るのか」を考える
『文明の生態史観』(梅棹忠夫、中公文庫)
 歴史の教科書を見れば、世界は「西洋」と「東洋」という大きな枠組みで分類されている。自身の経験を通じ、1950年代に既に、その枠組みに限界を感じた歴史家がいる。梅棹忠夫である。
歴史の教科書を見れば、世界は「西洋」と「東洋」という大きな枠組みで分類されている。自身の経験を通じ、1950年代に既に、その枠組みに限界を感じた歴史家がいる。梅棹忠夫である。
1955年に梅棹がアフガニスタン、インド、パキスタンを調査旅行し、彼が見聞きして感じたことをまとめたのが本書である。日本と欧州は封建制から隠健な革命を経て飛躍的な発展をする、という比較的安定した歴史を歩んだのに対し、両者に挟まれた広大な東欧、ロシア、中東、アジアは建国と侵略、過激な革命を繰り返し、基本的には専制君主国家しか成立し得なかった。前者を「第一地域」、後者を「第二地域」と梅棹は命名し、その政治、文化、人々のマインドセットに大きな違いがあることを見出した。
西洋、東洋という分類において日本は東洋に属し、アジア地域に対しては欧米諸国よりは近しいという一定の親和性の前提を持って企業は進出していく。しかし、アジアと日本に親和性など、それほどないのでは。数千年の歴史と地理をベースにした、異なる視点からのグローバル観を養うきっかけとなる1冊である。
「日本人は本当に多様ではないのか」を考える
『DNAでたどる日本人10万年の旅』(崎谷満、昭和堂)
 日本は島国であり、ほぼ単一民族だから均質性が高く、多様性の受容が苦手、というのが私たちに刷り込まれた日本人観である。しかし、本書では、Y染色体のDNA多型解析による人類の移動の歴史の追跡によって、新たな日本人像を提示している。
日本は島国であり、ほぼ単一民族だから均質性が高く、多様性の受容が苦手、というのが私たちに刷り込まれた日本人観である。しかし、本書では、Y染色体のDNA多型解析による人類の移動の歴史の追跡によって、新たな日本人像を提示している。
約10万年前にアフリカ大陸で誕生した現生人類は、アフリカにとどまった2つのDNA系統を除き、3つの系統が異なるルートをたどって世界に散っていった。他国・他地域では一定の系統の集積が見られるのに対し、日本では3系統に由来する多様な型が共存する。これは世界的に見て非常に珍しいという。「民族の存亡をかけた凄まじい戦争の歴史が大幅にDNA地図を塗り替えた」ユーラシア大陸東部のように、その系統のホームランドですら祖先のグループが途絶えている場合がある。日本でDNAの多様性が維持できた背景の1つには、大陸から新しい技術を携えてきた人々をいつの時代も受け入れ、平和的に共存したことがあるという。
本書が提示するのは、日本人がDNAレベルでは多様であり、内なるグローバル化が十分に可能な受容性を持つという事実だ。では、なぜ私たちは自らをそう認識できないのか。そこが人事の考えるべき点である。
「仕事観の変容にどう向き合うのか」を考える
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(マックス・ヴェーバー、岩波文庫)
 人は何のために働くのか。仕事に対する価値観は、歴史的に見ても、社会環境によって変化してきた。マックス・ヴェーバーは本書のなかで、禁欲的なプロテスタンティズムの倫理こそが勤勉さを生み、近代資本主義の誕生に貢献してきたと説く。神は救われるものと救われないものをあらかじめ定めているという二重予定説は、神から課された使命(仕事)に専心し、衝動や欲求を厳しく統制する現世的な「禁欲」を人々にもたらした。資本主義の発展には、現在の消費のためではなく、将来の救済のために働くというプロの消費のためではなく、将来の救済のために働くというプロテスタンティズムの新しい労働価値観が、心理的準備として必須だった。ところが資本主義が発展すると、神から課された使命に応えるという内的動機は消え、利潤という外的動機の追求に仕事観は変容した。現代資本主義の存続の危機を、20世紀初頭にヴェーバーが強く訴えている。
人は何のために働くのか。仕事に対する価値観は、歴史的に見ても、社会環境によって変化してきた。マックス・ヴェーバーは本書のなかで、禁欲的なプロテスタンティズムの倫理こそが勤勉さを生み、近代資本主義の誕生に貢献してきたと説く。神は救われるものと救われないものをあらかじめ定めているという二重予定説は、神から課された使命(仕事)に専心し、衝動や欲求を厳しく統制する現世的な「禁欲」を人々にもたらした。資本主義の発展には、現在の消費のためではなく、将来の救済のために働くというプロの消費のためではなく、将来の救済のために働くというプロテスタンティズムの新しい労働価値観が、心理的準備として必須だった。ところが資本主義が発展すると、神から課された使命に応えるという内的動機は消え、利潤という外的動機の追求に仕事観は変容した。現代資本主義の存続の危機を、20世紀初頭にヴェーバーが強く訴えている。
翻って現代の日本はどうか。物質的豊かさを背景に、多くの人が自己実現という内的動機づけを重視するようになった。しかし企業は、全員の自己実現を満足させられない。変化した個人の仕事観と組織的ニーズのミスマッチ問題に、向き合うときがきている。
「日本は農業中心の社会だったのか」を考える
『日本の歴史をよみなおす(全)』(網野善彦、ちくま学芸文庫)
 現在にいたる私たちの生活の大きな枠組みは、室町時代の少し前、南北朝動乱期の14世紀から続くと、網野善彦は本書のなかで述べている。たとえば「町」や「村」という単位はこの時期にできたという。
現在にいたる私たちの生活の大きな枠組みは、室町時代の少し前、南北朝動乱期の14世紀から続くと、網野善彦は本書のなかで述べている。たとえば「町」や「村」という単位はこの時期にできたという。
なかでも注目すべき指摘は、「日本は農業社会」であるというのは誤解とする点である。独特の日本文化を支えているのは水田を中心とした農業であり、弥生時代以降、江戸時代までそれは続き、産業社会に移行するのは明治時代以降だとするのが一般的な認識だ。しかし実際には、貿易業や金融業などを農業とともに営む多角的経営をしていた人々が多く存在した。土地を持たず貧しいとされた農民の多くは、さまざまな商売を営んでいたために、土地を持つ必要がなかったというのだ。これらの事実を通じ、農業中心の均質的、斉一的な文化を持つ日本人像ではなく、起業家精神に溢れる新しい日本人像を私たちに提示する。もし網野の指摘どおり、我々の先祖が兼業、起業、イノベーションを厭わぬ機を見るに敏な知恵者だったなら……。私たち自身が常に口にする「日本では、日本人には、難しい」という言い分は、直ちに根拠を失うのである。
「日本の集団主義は強みか」を考える
『日本の「安心」はなぜ、消えたのか』(山岸俊男、集英社インターナショナル)
 日本という国、あるいは日本企業の「集団主義」を否定する人は少ない。社会学者・山岸俊男は本書のなかで、その集団主義は、組織との積極的な一体感や忠誠心を基盤としたものではなく、組織から放り出されては生きていけないというリスク回避の集団同調圧力によるものだと看破した。これを著者は、「安心社会」と呼ぶ。安心社会には、「メンバーがお互いを監視し、何かあったときに制裁を加えるメカニズム」が埋め込まれている。「言い換えれば、日本型集団主義社会とは、社会の仕組みそのものが人々に『安心』を提供することによって、いちいち他人を『信頼』しなくてもいいようにしてくれる社会」だという。
日本という国、あるいは日本企業の「集団主義」を否定する人は少ない。社会学者・山岸俊男は本書のなかで、その集団主義は、組織との積極的な一体感や忠誠心を基盤としたものではなく、組織から放り出されては生きていけないというリスク回避の集団同調圧力によるものだと看破した。これを著者は、「安心社会」と呼ぶ。安心社会には、「メンバーがお互いを監視し、何かあったときに制裁を加えるメカニズム」が埋め込まれている。「言い換えれば、日本型集団主義社会とは、社会の仕組みそのものが人々に『安心』を提供することによって、いちいち他人を『信頼』しなくてもいいようにしてくれる社会」だという。
日本企業はこの安心社会の文脈のうえに、メンバーシップ型の雇用システムや現場における「あうん」の関係、系列取引の構造などを築いてきた。これらは組織間、個人間の取引コストを低減し、日本企業の強みとなった。しかし、不確実なグローバル世界に打って出ようとするとき、安心社会のコンテクストが弱みになる可能性はないのか。そんな問いかけが必要だろう。
「価値観はどのようにして社会に刷り込まれるのか」を考える
『タテ社会の人間関係』(中根千枝、講談社現代新書)
 中根千枝は本書において、日本社会を「タテ社会」と呼んだ。まず、社会集団はその構成要因によって、「資格」(職業、身分、血縁といった属性の共通性)中心の集団と、「場」(村、会社、大学といった地域・所属などの枠)中心の集団に分かれる。日本社会はもちろん後者だ。「場」を強調する社会では、同一集団内に序列が生まれる。誰でもやればできる、という「能力平等観」が根強い日本においては、個人の能力には無関係の生年、入社年、派閥などが序列を決める。変化の兆しはあるが、1967年の出版から約50年を経た今も、厳然と組織のなかには給与、昇進、受けるべき研修まで、年次管理が根強く残る。私たちは今も、タテ社会に生きている。年齢や入社年次以外に能力差はないとするタテ社会だからこそ、出世できないとみじめになる。
中根千枝は本書において、日本社会を「タテ社会」と呼んだ。まず、社会集団はその構成要因によって、「資格」(職業、身分、血縁といった属性の共通性)中心の集団と、「場」(村、会社、大学といった地域・所属などの枠)中心の集団に分かれる。日本社会はもちろん後者だ。「場」を強調する社会では、同一集団内に序列が生まれる。誰でもやればできる、という「能力平等観」が根強い日本においては、個人の能力には無関係の生年、入社年、派閥などが序列を決める。変化の兆しはあるが、1967年の出版から約50年を経た今も、厳然と組織のなかには給与、昇進、受けるべき研修まで、年次管理が根強く残る。私たちは今も、タテ社会に生きている。年齢や入社年次以外に能力差はないとするタテ社会だからこそ、出世できないとみじめになる。
日本社会に成果主義がなじまないのも当然だ。さらに課題はある。意思決定の基本原則は、情報・能力・権限の一致である。第一線での個別性が高い仕事、想定外の事態への対応、専門性が高い仕事は、序列が基本の意思決定システムでは難しい。序列から役割へ。固定から柔軟へ。変化の時代に組織モデルを適合させられるか、という課題が浮かび上がる。
「日本企業の組織に内在する問題とは何か」を考える
『失敗の本質』(野中郁次郎ほか、中公文庫)
 ノモンハン事件、ミッドウェー作戦など第二次世界大戦前後の日本軍の失敗の連続を、組織としての日本軍の失敗としてとらえ直した本書は、人事必読の書だ。
ノモンハン事件、ミッドウェー作戦など第二次世界大戦前後の日本軍の失敗の連続を、組織としての日本軍の失敗としてとらえ直した本書は、人事必読の書だ。
日本軍は、日清戦争、日露戦争の成功体験のせいで、大艦巨砲主義、白兵銃剣主義から抜け出せなかった。そのため、空母や戦車などの装備が重視されなかったばかりか、必要な人材像の見直しも行われなかったのだ。当時、陸軍大学校では、記憶力に優れ、意志強固なものが優秀とされた。いったん優秀な成績で卒業したものは戦略参謀となり、戦いの結果にかかわらず温存され、同じ過ちを繰り返した。米国では変化に素早く対応し、開戦と同時に主要な司令官ポストを、戦時向けに若返らせたにもかかわらず、だ。
こうしたエリート選抜主義、そこに始まる人物評価の固定化、過去の成功体験からくる上部構造の固定化は、現在の日本企業の課題と重なって見える。組織が同じ失敗を繰り返さず、変化対応力を有するために何ができるのか。それらが人事に問われている。
「人はどれほど強い、あるいは弱いのか」を考える
『自由からの逃走』(エーリッヒ・フロム、東京創元社)
 エーリッヒ・フロムは本書の序文で、「本書は近代人の性格構造についての、また心理的要因と社会的要因との交互作用という問題についての広範囲な研究の一部」と述べている。具体的には、ナチズムに傾倒していったドイツ社会とそこに生きた人々の心理の考察であり、その基盤には外界の影響を受けた無意識の力が、人の心理と行動に大きく影響を与える、というフロイトの理論がある。
エーリッヒ・フロムは本書の序文で、「本書は近代人の性格構造についての、また心理的要因と社会的要因との交互作用という問題についての広範囲な研究の一部」と述べている。具体的には、ナチズムに傾倒していったドイツ社会とそこに生きた人々の心理の考察であり、その基盤には外界の影響を受けた無意識の力が、人の心理と行動に大きく影響を与える、というフロイトの理論がある。
近代以前の欧州の人々は、生まれたときから家族や共同体といった構造のなかにあった。近代に入り、資本主義の発達によって「自由」を獲得し始めた。しかしながら、「自由」と「孤独」は切り離せない。個人、特に中産階級や農民のなかには、それまで依拠していた集団からの解放によって、孤立感や不安に苛まれる人が多く存在した。この状況をフロムは「自由からの逃走」と呼び、大きな環境変化がドイツ市民の無意識に作用しヒトラーを称え、喜んで服従するという行動に駆り立てたと分析した。
人が備える絆への潜在的欲求が悪い形で現れれば、集団の同化圧力の暴走につながる。そして、人は無意識への刷り込みに大きく揺さぶられる。人事は、組織とその規範が働く人々を縛りつけることの怖さ、縛りつけているからこその人々の弱さに自覚的であらねばならない。
「キャリア自律の重要性とは何か」を考える
『50歳までに「生き生きした老い」を準備する』(ジョージ・E・ヴァイラント、ファーストプレス)
 本書の原題は"Aging Well"だ。ハーバード大学による、思春期から老年期までの約800人の生涯にわたる追跡調査から、「幸福な老い」の要因を導き出した意欲作である。その要因は、遺伝子でも貧富でも人種でもない。①非喫煙者か若いころに喫煙をやめていること、②成熟した適応的対処方法を獲得していること、③アルコール依存症ではないこと、④健康体重を維持、⑤安定した結婚生活、⑥定期的な適度の運動、⑦高学歴、という7つだ。特に2が重要で、よき歳の重ね方をしている人は、人生のうちのコントロールできること・できないことを区別し、コントロールできることにどう対処・チャレンジするか、できないことをどう前向きに受容するか、長期的視点で冷静に行動を変えられる思考行動特性を持つ。彼らは自分で行動を選択し、それを実行に移している。
本書の原題は"Aging Well"だ。ハーバード大学による、思春期から老年期までの約800人の生涯にわたる追跡調査から、「幸福な老い」の要因を導き出した意欲作である。その要因は、遺伝子でも貧富でも人種でもない。①非喫煙者か若いころに喫煙をやめていること、②成熟した適応的対処方法を獲得していること、③アルコール依存症ではないこと、④健康体重を維持、⑤安定した結婚生活、⑥定期的な適度の運動、⑦高学歴、という7つだ。特に2が重要で、よき歳の重ね方をしている人は、人生のうちのコントロールできること・できないことを区別し、コントロールできることにどう対処・チャレンジするか、できないことをどう前向きに受容するか、長期的視点で冷静に行動を変えられる思考行動特性を持つ。彼らは自分で行動を選択し、それを実行に移している。
日本人の多くに、キャリア自律は浸透していない。自身のキャリアを自ら選択(計画)しない限り、満足感の高い歳の重ね方はできない。70歳まで働く時代のキャリア支援に一石を投じる1冊である。
「20世紀型の経営からいかに脱却するか」を考える
『経営は何をすべきか』(ゲイリー・ハメル、ダイヤモンド社)
 経営思想家ゲイリー・ハメルは、本書において、20世紀型経営の課題を管理型の経営だと指摘し、その時代の終焉を示している。同時に、グローバルにおける幅広く多様な要因が経営環境に影響を与え、経営の予測可能性が低下してしまった。そのなかにあって、資本主義、組織、働き方など根本的な「経営の常識」を問い直し、未来にも人間にも適した組織をいかにつくるかを説いた。
経営思想家ゲイリー・ハメルは、本書において、20世紀型経営の課題を管理型の経営だと指摘し、その時代の終焉を示している。同時に、グローバルにおける幅広く多様な要因が経営環境に影響を与え、経営の予測可能性が低下してしまった。そのなかにあって、資本主義、組織、働き方など根本的な「経営の常識」を問い直し、未来にも人間にも適した組織をいかにつくるかを説いた。
ハメルによれば、これからの経営が重視すべきことは、理念、イノベーション、適応力、情熱、イデオロギーの5つである。これらは管理型の経営に求められることとは一線を画す。
未来型の経営をするには、20世紀型のリーダーたちの背中を見て学ぶだけでは、到達できない。それらから意図的に脱却し、新しい習慣を身に付けることが、これからの経営者の必須条件であることを、人事も理解しておくべきだろう。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ