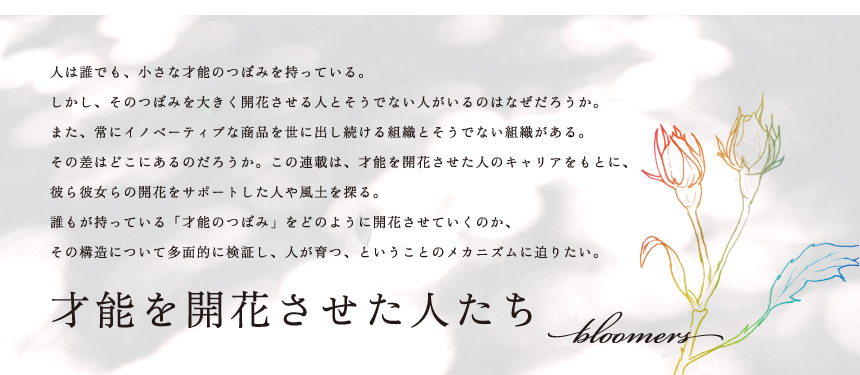
07. 青山社中 代表取締役 (兼筆頭代表CEO) 朝比奈一郎氏

「国や社会のために働くってかっこいい」
中学生からの夢をかなえて、官僚となる
朝比奈氏は東京大学法学部を卒業し、1997年、通商産業省(現・経済産業省、以下同)に入省した。そのきっかけとなったのは、当時珍しかった全寮制の男子校で中学・高校時代を送ったことにあるという。「先生も熱心に教えてくださる方ばかりで、特に大野俊正先生、吉川幸次先生はもう、ほとんどいつも学校にいらっしゃって、頑張ることのすごさを教えられました。また、テレビ禁止の寮で、低学年は4人部屋でした。やることがないので、毎晩ただ語り合うことと読書で時間を過ごしていました。特に司馬遼太郎や城山三郎の本にはまっていました」(朝比奈氏)。その生活のなかでぼんやりと「国や社会のために働くってかっこいいな」と思い始めた朝比奈氏は、政治への関心を深めていった。当時、日米通商交渉のニュースを見て、日本は交渉の場面で押されていると感じ、将来は自分がその場に立ちたいという思いを強くした。「そのためには東大に行かなきゃだめだ」と思い立ち、先生に相談したところ、一笑に付された。しかし逆にやる気に火が付き、一浪して無事念願の東京大学法学部に合格した。大学では政治家を多く輩出している弁論部に所属した。そのつながりで、現役の政治家をはじめ、官僚となった先輩たちに話を聞く機会が多くあって、「官僚も面白そうだ」と感じ、国家公務員の道を選択したのだ。
“人”に惹かれて通産省に
国際交渉より難しい省庁間交渉の現実を知る
当初は治安や安全保障への関心が高かったので、警察庁と防衛庁(当時)を志望していた朝比奈氏。しかし、試験を受けたあとで、志望する省庁を選んで訪問する日程に空きがあったことから、「人気のあるほかの省庁も見てみよう」(朝比奈氏)といくつかの省を訪問した。そこで、省庁ごとのカルチャーの違いに接し、急速に心を動かされた通産省への入省を決断することになった。ただ当時は、「通産省不要論」がささやかれていた時代で、「本当に迷ったのですが、通産省の仕事を一人称で語る人の多さに惹かれて」(朝比奈氏)、最後は徹夜で悩んで決めたのだという。その後、9週間にわたる初任者の長期研修を経て、通商政策局経済協力課に配属になった。その年にアジア経済危機が起き、日本として何か援助できることはないかということから、「特別円借款」という制度を作ることになった。この制度は、資金を提供してその資金を使った仕事を日本企業が受注するという仕組みなのだが、このルール策定にあたっては、当時の大蔵省(現・財務省)、通産省、外務省、経済企画庁(現・内閣府)の4省庁で意見をまとめる必要があった。各省庁の思惑が錯綜し、対立する意見の調整に時間ばかりが過ぎ調整は難航、連日午前3時、4時まで働いていた。当時の上司の平田竹男氏(現・内閣官房参与)は、そんななかでも抜群の突破力を発揮し、強引に交渉を進めていく実力者だった。リーダーシップとは突破力だと考える朝比奈氏の原点となる上司であった。国際交渉以前に、省庁間での交渉の難しさを痛感し、何か仕組みが間違っているのではないか、朝比奈氏はそんな疑問も抱き始めた。
初任者長期研修で出会った同期
ボストンで改革への思いを語り合う
2000年に特許庁に異動した朝比奈氏は、組織や人員について考える総務課総括係長として、人員増強の必要性を感じて総務省に働きかけていくものの、まったく思うようにならない閉塞感を感じていた。そんな時、朝比奈氏に留学のチャンスが巡ってきた。英語への苦手意識を克服したいという思いもあり、猛勉強してハーバード大学ケネディスクールに合格することができた。渡米直前までの仕事があまりにも多忙だったこともあり、留学先で少し考える余裕が生まれてみると、外から見た日本の政策立案や業務の進行に疑問が深まった。ケネディスクールには各国の行政官が集まっており、彼らと情報交換する中で日本の行政組織の特異性も見えてきた。たとえばアメリカの行政官には、その道の専門家が付いている。経済対策なら経済学博士として大学で教えられるだけの実力がある人間が、政策を作っている。翻って日本を見てみると、地頭の良さを重視した採用で、専門性はあまり重視されていない。朝比奈氏自身も法学部の出身だが、経済政策を担当している。予算査定のあり方も、日本ではまず前例が問われるが、アメリカでは「先んじれば世界のトップに立てる」という問題意識で策定されるなど、外から見るからこその日本の行政組織の問題点を感じるようになっていった。朝比奈氏はその疑問や自身の考えを仲間たちと共有し始めた。ちょうど同じ時期に、初任者研修をともに過ごし各省庁にちらばった同期たちがアメリカに留学していた。研修では省庁の壁を越えて何度も議論し、語り合ったこともあり、この問題意識をぶつけるとすぐに共感を得ることができた。まず、ミラキュース大に留学していた小紫雅史氏(当時・環境省、現・生駒市副市長)がボストンを訪ねてくれて語り合い、その後も、シカゴで、ニューヨークで、ロンドンで、一人ひとりと課題を共有した。同じ頃、一足先に戻っていた同期の仲間も巻き込んで10人ほどで、改革に向けて何かしようという思いが高まっていった。
「アクティブ ノン アクション」
だったら、第3の道を選ぼう
帰国前に、「このまま帰国して行政の現場に戻っていってもいいのか」と悩んだ朝比奈氏。「みんな毎日本当に忙しく働いているけれど、結果として何を成し遂げているのだろう。日本を取り巻く本質的な課題は何も解決できていない。今思えばアクティブ ノン アクションなんじゃないか」(朝比奈氏)という思いが募っていった。当時、若手で優秀なキャリア官僚が官庁を辞める動きが増えていた。自分たちはどうしたいのかを考えるなかで、「国や社会のために何かしたい」(朝比奈氏)と思って入省したのに、このまま辞めてしまうのも、偉くなって実行できるまでじっと我慢するのも、どちらもしっくりこなかった。第3の道として「中から改革を仕掛けよう」(朝比奈氏)と考え、朝比奈氏が代表、小紫氏が副代表として作ったのが、「プロジェクトK(新しい霞ヶ関を創る若手の会)」だ。そして、2003年9月に帰国したあと、朝比奈氏は留学中の思いを実現すべく、小紫氏ら仲間たちと定期的に集まって問題を洗い出す議論を始めた。議論が進むにつれ、さらに組織、人事、業務改善の部会を作り、仕事を済ませたあと連日のように議論を具体化していった。2年間の議論を経て、2005年に『霞ヶ関構造改革・プロジェクトK』を、新しい霞ヶ関を創る若手の会の名前で出版するに至った。当時、朝比奈氏は石油天然ガス課に所属しており、徹夜の交渉をするなど多忙を極めていたが、執筆はその合間を縫って手分けして進め、出版直前になって一斉にそれぞれの上司に報告することにした。「ちょうど2日徹夜を続けてハードな交渉を終えた朝、上司に報告したことを覚えています」(朝比奈氏)。著書の中で提言した霞ヶ関の人事制度改革案が、第一次安倍政権の時から本格化する公務員制度改革に反映され、また「政策統合機関たる総合戦略本部を創ろう」といった内容などが、民主党政権下での、国家戦略室などの形として日の目を見ることとなった。
霞ヶ関を変えるのがゴールではなかった
限界を超えて、外から日本を良くしていきたい
公務員制度改革の議論を進める事務局に、プロジェクトKのメンバーが起用されるなど、順調に存在感を増したかに見えるプロジェクトKだったが、朝比奈氏はなかからの改革の限界を感じ始めていた。改革のための組織は一応整っていたが、魂が入らない。政権がくるくる変わるなかで、本来やろうとしていたことがずれていく。プロジェクトKは2006年にNPO法人化していたが、その活動を進めるだけでは本当にやりたいことに届かないのではないかと考えるようになったのだ。「日本を良くしたいから改革をしようと思っていたはずなのに、霞ヶ関のなかのことだけやっていたのでは目的に届かない」(朝比奈氏)、という思いが強くなった。「重病人の治療をするのに、まず指の怪我を治しているようだ」(朝比奈氏)と感じ、本当に今、足りないことを自らの手で作り出すため、2010年、経産省を退職し、人材育成と政策づくりをテーマに、盟友の遠藤洋路氏(当時・文部科学省)とともに青山社中を設立するに至った。
次世代リーダーを育て、日本全体の課題を解決する
青山社中を現代の松下村塾に育てたい
失われた10年とも20年ともいわれる日本、中でもガバナンスの問題は根が深い。正解がどこかにあって、それを素早く探す力が必要とされていた時代から、誰も解いたことのない問題に立ち向かっていかなくてはならない時代になっている。朝比奈氏は、「今必要なのは、国や社会のことを考えたうえで変革を起こせるリーダーの育成と、政策を創る力だ」と考え、その2つの柱で事業をスタートさせた。現在、主要政党の政策作りや、地方自治体における改革、突破力のある人材育成など、幅広い分野で日本を立て直すべく東奔西走している。現在、青山社中が実施するリーダー塾で朝比奈氏のもとに集う若者たちは、そんな朝比奈氏から強い決意を持ったリーダー像を学んでいくことだろう。
(TEXT/柴田 朋子)



 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ