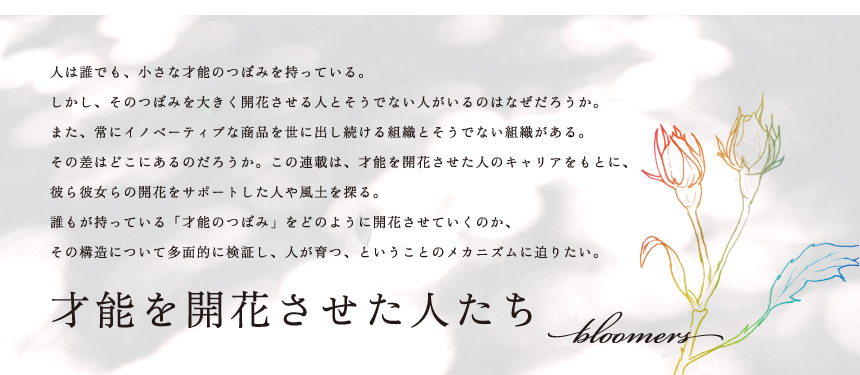
02. 象印マホービン 第一事業部マネージャー 後藤譲氏

希望した営業部門から、
予想外の本社経営企画室への異動
埼玉県出身の後藤氏は、1996年に新卒で入社し、最初は地元の営業拠点、関東支店に配属となった。営業は、自らが希望した職種だった。7年半の間、順調に実績をあげていたが、2004年、当時としてはめずらしい地域間異動で本社の経営企画室へ移ることになった。「いい異動だ。めったに行ける部署ではない」と労働組合の委員長にも言われたほどの抜擢人事だった。
異動先の経営企画室では、他部署の人たちと交流することを心がけ、飲み会にも積極的に参加していた。経営企画室室長の山地哲夫氏からは、営業とは違う仕事の進め方、ものの考え方を徹底的に教わり、大いに影響を受けた。のちに山地氏は生産部門のトップとなり、後藤氏が進める炊飯ジャープロジェクトにも関わりを持つことになる。経営企画室では、若手は3~5年間経験を積んだあと、他部署に出るのが通例で、後藤氏も4年で異動となった。営業は経験したのでそれ以外を希望していたところ、商品企画部に。異動2年目で、中核商品である炊飯ジャーの担当になった。
若手、未経験、非管理職が
重いプロジェクトのリーダーに抜擢
その頃、象印マホービンでは、高級炊飯ジャーの売り上げが伸び悩んでいた。いったん陰りが出るとメディアの取り扱いも減り、売り上げが落ちる。この悪循環への危機感から、部門横断型の30~40代を中心とした若手社員による炊飯ジャープロジェクトが立ち上げられ、炊飯ジャー担当になったばかりの36歳の後藤氏は、そのリーダーに抜擢された。後藤氏は、炊飯ジャーについてはまったくの素人で、しかも開発の経験もなく、管理職でもなかった。プロジェクトの推進役が当時の商品企画部部長であった上司の宇和政男氏であったことから、「やってみろ」と指名を受けることになったのだ。当時は「正直、はずれくじひいたかな」(後藤氏)という思いもあったという。 開発のベテランや炊飯ジャーに詳しい年上の社員、ふだん開発プロジェクトには参加しない販売促進や広報など、幅広い部門から集められた14人体制の大プロジェクトだった。しかも、上から伝えられたミッションは、「満足してもらえる商品をお客様に届ける」という抽象的なもの。具体的な開発の方向性は後藤氏に委ねられた。 まず後藤氏は、全員で夢を語る場を作った。日々の仕事では、部門ごとに目の前の課題解決に追われ、「どちらかというとマイナスをゼロにする仕事」(後藤氏)を多くやっていたので、それを横において、大風呂敷を広げてもらおうと、夢を語るところからスタートさせたのである。
本当においしいご飯が炊ける釜を。
「飯炊き仙人」の向こうを張る
同社にはもともと、象印流の美味しいご飯の定義があり、開発現場ではそれに何の疑問も持っていなかった。後藤氏は素人だからこそ「それって本当なの?」と、メンバーに問いかけた。検証するために自分たちの美味しいご飯の定義と、ご飯がおいしいといわれている人気店20~30店舗を比較してみることにした。メンバーで手分けをして食べ歩いていたある日、後藤氏は「これだ!」という味に遭遇した。堺にある銀シャリ屋「げこ亭」という定食屋だ。「我々の定義した美味しいご飯によく似ていた。この方向でよかったのだ」。そう後藤氏は確信した。
忙しさのピークを過ぎた時間を見計らって、店の奥に声をかける。80歳近い主人村嶋孟氏は、「美味しさの秘密を知りたい」という後藤氏の話に黙って耳を傾ける。そして、「ええよ」と快諾。お客様に美味しいご飯を提供したい、という思いは共通だった。村嶋氏は業界では「飯炊き仙人」と呼ばれるほどの有名人で、ご飯へのこだわりは生半可ではない。しかし、店の跡継ぎは決まっていなかった。「自身の技術を伝えたいという思いもあったのかもしれません」(後藤氏)。
翌週、開発担当の宇都宮定氏とともに再訪。村嶋氏の協力を得て、徹底的に炊き方のメカニズムを分析し、データを採った。かまど、釜やふたの形状、内部の温度変化など、あらゆる角度から検証した結果、炊きむらが見事なほどにないことが判明した。 当時の自社製品には炊きむらがあった。どうしたらそれをなくせるのか、ここから開発はスタートした。「横からの加熱」。これが答えだった。しかしそのためには、炊飯ジャーの内釜として、数々の賞を受賞し、当時上位機種に搭載していた真空かまど釜を見直さなければならない。真空かまど釜は、内釜側面が真空であるがゆえに、側面からの加熱がしにくいからだ。
同社の売りは、マホービンで培った真空技術である。このコア技術を否定することになる。営業からは、今までのセールストークと矛盾するという不安の声があがる。長く炊飯ジャーの開発に携わった開発担当者たちも複雑な反応を示す。それでも、彼は信念を曲げなかった。真空技術を否定するのではなく、その技術の延長線上に、本体から熱を逃がさない空気断熱層を持つ羽釜の形状があるのだと発想を変え、社内プレゼンに臨んだ。そこで実際に羽釜(はがま)でご飯を炊いて見せたところ、そのインパクトがすごかった。一目でわかる粒の大きさとつやに、全員が圧倒された。「羽釜でいこう」。この時点で企画方針が決まった。炊飯ジャープロジェクト発足から10カ月後のことだった。
その後、商品化された圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」(通称:極め羽釜)は、瞬く間に大ヒット商品となっていくのである。
信頼して見守ってくれる上司と、
心を許せる仲間に支えられた
後藤氏をリーダーに据えた宇和氏は、長年、炊飯ジャーの企画担当として有力商品を世に送り出してきた人物だ。しかし、自分たちの代がやっていては革新的な商品は開発できないという考えのもと、このプロジェクトを若い後藤氏に託した。託すだけでなく、途中プロジェクトが難航し、後藤氏の士気が下がりそうになったり煮詰まってきたりすると、さりげなくアドバイスをくれた。プロジェクトを常に見守り、後藤氏の支えとなってくれた上司だった。
心を許せるメンバーにも恵まれた。プロジェクトには開発系と営業系の分科会があり、開発系では炊飯ジャーのプロである宇都宮氏が、営業系では岡村健治氏が年下の後藤氏を支えていた。またデザイン面では、気心の知れた同期の岡島忠志氏が、後藤氏の無理難題を引き受け、相談にものってくれた。未経験での重いプロジェクトへの挑戦は、このような仲間たちに支えられて果たすことができたのだ。
「モノづくりからコトづくりへ」
商品づくりのスタイルが、人材育成にも通じる
羽釜にすることによって、平たい形状になり、内径が広くサイズが大きくなる。当時コンパクトな商品が主流になっていた中で、大型化は明らかにデメリットだった。しかし、美味しくするためには必要なことだという確信はあった。社内だけでなく、社外向けの試食会などを通して、この味に惚れ込んでもらうこと、開発の経緯を共有して共感してもらうことを重視した。結果として、営業だけでなく、思い入れをもって拡販してくれる店舗が出てきた。また、羽釜の成功がきっかけとなって、全社で「モノづくりからコトづくりへ」という流れが生まれた。いい商品をつくるだけでなく、そこに開発者の思いを込めたストーリーをのせていく必要がある、という意識の変化である。
このプロジェクトの成功が、社内の若手の育成においても好事例となり、また、「極め羽釜」を知って、入社を希望する学生も出てきた。 今も「げこ亭」の村嶋氏には、新製品の味をチェックしてもらっている。彼の承認がない限り新商品にはしない。「私は村嶋さんを師匠だと思っています。村嶋さんも私たちのことを認めて下さっています。」(後藤氏)。
(TEXT/柴田 朋子)



 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ