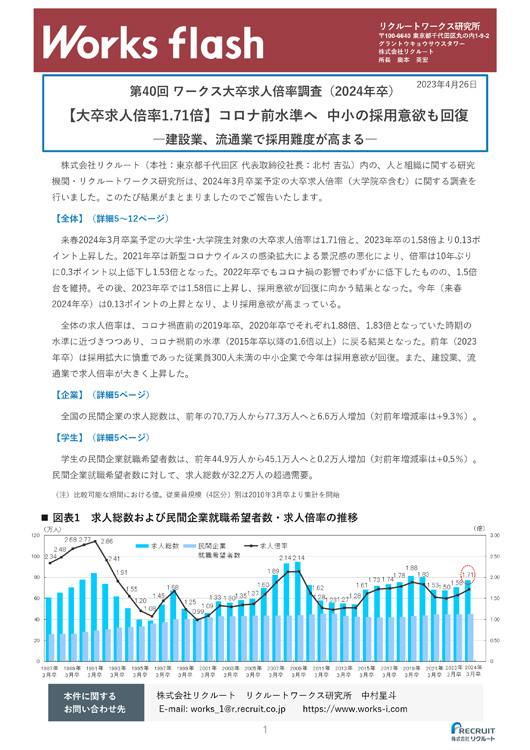あいまいな「〇〇力」による選考を問う 学びを評価する仕組みへ転換を
少子高齢化で若年者が貴重な戦力となる中、採用選考は企業と学生、双方の成長に資するあり方へと変わることが求められている。教育と職業の接続を研究する東京大学の本田由紀教授(教育社会学)とリクルートワークス研究所の中村星斗研究員・アナリストが、選考にまつわる課題と今後進むべき方向性について語り合った。
ひそやかに存在するレリバンス 採用では評価されない
本田:私は教育の職業的意義(レリバンス)、つまり教育がその後の職業にどのように役立つのかを研究しています。日本は諸外国に比べ、職業的レリバンスが希薄だとされています。学生が学びにかけた時間とお金、そして良い授業をしようという教員の努力は本当に無駄になっているのか、だとしたらそれでいいのかという問題意識が研究の出発点です。
人文学・社会科学の分野で、学びの習得度と職業的な成果の関係を追跡調査した結果、大学での学びは、仕事のさまざまなスキルを高めていることを確認できました。職業的レリバンスは存在しているもののひそやかであり、それが表に出ず隠されていることが問題だったのです。
中村:私は大学1年生の春、ある授業を担当していた教員が「文系の学問は役に立たない」と言っていたのを聞いて驚いた覚えがあります。文系学問の職業的レリバンスは、教員にすら認識されないほどに「隠された」存在だということでしょうか。
本田:大学での学びは、問いを立ててそれを解き明かす経路を探し、実践して論文を書くという高度な知的作業であり、仕事の役に立たないはずがありません。しかし私も、ある文系学部の教授が高校生たちに向かって「大学の授業は仕事の役には立ちません」と話すのを聞いたことがあります。学問は実用性から距離を置いた方が高尚だという考えから言ったのでしょうが、大学教員が自分の提供する教育を「役に立たない」と言い切ることに憤りを覚えました。
しかし職業的レリバンスが隠されている大きな要因は、学生の知的な成果をあまり評価しない就職や選考の仕組みにもあると考えます。
〇〇力が、不公正な選考の隠れ蓑に あいまいな基準に苦しむ若者
中村:若手社員に就活の話を聞いて、「学生時代に最も力を入れたことは勉強ですが、面接では別の話をしました」と言われたことがあります。アルバイトやサークル活動の経験は評価されるが学業はそうではないと考えていたようです。明らかに学生時代の学びが仕事に役立っているのに、その自覚がない若手社員もいます。
本田:アルバイトやサークルの経験は「円滑に対人関係を結ぶ力がある」と見なされます。一方で、学業から得られた知的な力は理屈っぽく受け取られる可能性もあります。日本企業はいまだに、会社に入ったらメンバーシップの一員として、組織になじんでもらうことを重視しているのです。
中村:本来、選考はシンプルに仕事に役立つ力を評価すればよいと思います。しかし実際は「コミュニケーション能力」や「主体性」など「何となくいいと思える」能力が持ち込まれていると感じます。これらの能力が仕事の役に立たないわけではないですが、問題はそのあいまいさにあるように感じます。
本田:なぜ「〇〇力」「カルチャーフィット」といったあいまいな基準で、大切な採用の判断ができるのか不思議です。こうした言葉は、好きなタイプの人を恣意的に採用したり、女性や留学生などへの差別を持ち込んだりといった、不公正な選考の隠れ蓑になるリスクを抱えています。また、「〇〇力」が人格や性格など、人間性の根幹に関わる部分を指すことも問題です。そこを評価され、「不採用」と判断されたときには、学生は人格を全否定されたような感覚に陥りかねません。
中村:今、選考の場で注目されるもののひとつに「主体性」があります。しかしながら、「この会社でやりたいことは何ですか?」と主体性を問う質問に答えて内定を得た学生が、入社後にやりたいことを主張すると「わがままだ」「まずは言われたことをできるようになってほしい」と言われてしまうなど、矛盾を感じることもあります。
本田:かつて「行動力」に近かった「主体性」の意味は今、「上司の意図を汲み、あたかも自発的であるかのように実行する力」にすり替わっています。企業や教育現場にとって都合のよい「主体性」に、言葉の意味が変わっていったのだと推察されます。若者の立場で考えれば、あいまいな「主体性」が押し付けられていると感じることもあるでしょう。
ジョブ型導入でスキルベースの採用へ 経済の凋落に歯止めをかける
中村:あいまいな要素で人を測ることはそもそも難しく、先ほど本田先生も仰っていたように、人間性に近い要素で不採用になったと感じることは、学生にとって苦しいことだと感じます。それなら、教育で身に付けたスキルなど「外付け」の機能を評価した方が、学生の苦しみは軽減され、結果的に企業のパフォーマンスも高まるのではないでしょうか。この場合、契約で職務が限定されるという意味でのジョブ型的な働き方は一つの解決策になり得ると考えます。
本田:確かにジョブ型はスキルを評価するので、人格や感情に手を突っ込むような選考は避けられます。また働く側は、職務外の仕事を断れるなど、経営側に対して一定の交渉力を持つことも可能になるでしょう。
ただ今のところ、ジョブ型を導入する企業は少数派です。日本の企業は労働者に自己主張されることに慣れていない上、人手不足のため若手のジョブを限定するより、むしろ今以上に幅広い業務に従事してほしいというニーズが強まっているためです。
例えばドイツはジョブに基づく採用基準が厳しく、志望企業の選考にすら進めない人が出てくるなど、ジョブ型にも課題はあります。一方、日本の採用システムは誰にでも門戸を開いているように見えますが、選考プロセスの不透明さという、ドイツとは違った意味での深刻な問題を抱えています。
若年労働市場は質のミスマッチ 若者は「こずるく」生きよ
中村:90年代以降の若年就職の問題の中心は「就職できない」ことでした。これは「量」のミスマッチングと捉えられます。一方、労働力不足の状況で就職難が後退する中では、学生と企業の「質」のマッチングの問題が出てきたように思います。
本田:確かに全体の求人倍率を見れば、新卒で学生が就職できないという状況は緩和していますが、質的な意味で学生と企業、双方にとってストレスフルな状況は続いています。学生から見れば、大企業に入るための競争に加えて、昨今は希望の配置を勝ち取るための「配活」まで行われるようになり、競争はむしろ苛烈になっています。企業側もリソースが限られる中、優秀な人材を早いうちに確保しようとして、インターンシップを含め採用選考がどんどん早期化しています。本来は学生がきちんと学び終えた、卒論後に選考を始めるのが望ましいと思います。
中村:確かに、卒論を終えた後というのは大学での学びが最も吸収された時期のように思います。学生と教育現場、企業が職業的レリバンスを認識し、企業のパフォーマンス向上や日本の経済成長につなげるには、どうすればいいでしょうか。
本田:日本はOECDのPIAAC(ピアック=国際成人力調査)で、読解力と数的思考力の平均得点が参加国中トップの成績でした。しかし教育で獲得した高いスキルは職場では十分に活用されておらず、スキルを活用する機会の男女差も大きいという結果も出ました。社員が手持ちのスキルをフル活用できる環境を整えれば、企業の生産性は高まるはずです。そのためには社員をあいまいな〇〇力ではなくスキルベースで評価するよう、選考のあり方を変える必要があります。
中村:学生は採用のルールがすぐには変わらないと見て、あいまいな評価基準のあんばいを想像しつつ、選考を切り抜けようとしているのかもしれません。しかし、ルール自体の正当性や妥当性を疑う力も身に付けてほしいと思います。 本田:これからの時代、ルールへの適応力だけを鍛えられた学生は、社会の変化に対応できず自滅してしまいかねません。その意味で、日本社会は今、貴重で大切にしなければならないはずの若年層に対して難しい状況を押し付けているとも言えます。
本田:これからの時代、ルールへの適応力だけを鍛えられた学生は、社会の変化に対応できず自滅してしまいかねません。その意味で、日本社会は今、貴重で大切にしなければならないはずの若年層に対して難しい状況を押し付けているとも言えます。
ただ一方、偏差値や企業規模にとらわれず、独自の生きる道を模索する若者も現れており、地殻変動は起きていると思います。
私は学生に「こずるく行こう」と言うことがあります。社会は改めるべき古い慣習やルールに満ちている。それをわかった上でしたたかに生き延び、時期が来たら変革に参加してほしい。学問の追究は、社会を批判する視点や、ルールそのものを疑う力を培う意味でも重要なのです。
中村:大学での学びと仕事とのつながりは、新卒採用のあり方や大学教育など、いくつかの要因によって隠されているということですね。現在は日本型雇用の見直し議論、働き方の変化など、若者を取り巻く環境が移り変わりつつある時代です。同時に少子化の中、企業には貴重な若年労働力を活かしていくことが、今まで以上に求められるようになっています。若者、企業双方にとってより良い状態を目指すためにも、「学びを活かす」というシンプルなことに改めて目を向けていく必要があると考えます。
執筆:有馬知子
撮影:平山諭


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ