
何を読み、何を見て、どんな対話をしてきたか
年間テーマ「コミュニケーションのデザイン」
コミュニケーションは誰かと共に何かを成すために欠かせないが、いざ向き合うと扱いに悩んでしまう。コミュニケーションそのものではなく、コミュニケーションを生み出している何かに目を向ければ、新たな視界が開けるかもしれない。そこで、私たちは、「キャラ」「茶道」「哲学」を題材に、デザインという観点から、コミュニケーションに対して抱いていた既存の思考を飛び出して考えるランダムウォーク(過剰な一歩)に挑んだ。
第1ユニットから第3ユニットまで、ほぼ同じ形式をとっている。各ユニットで「課題図書」の著者をゲストとして招き、話を聞き、さらにサロンメンバーの対話によって思考を深めていくというものだ。ここから各ユニットの内容と課題図書・参考図書を紹介していく。
2024年度 キックオフセッション
私たちはどのように「知のランダムウォークをするのか」
5月23日(木)@リクルート本社
「知の探索サロン」では何を目指すのか。それは、何かを学ぶことよりも、どのように学ぶのかという「学び方」を学ぶことにある。短時間で効率的にわかることを目指す収束的な思考ではなく、未知や未踏に飛び出すことで得られる拡散的な思考の醍醐味を、主宰である法政大学梅崎修先生に実体験を交えながら聞いた。
課題図書
『考えるとはどういうことか―0歳から100歳までの哲学入門』
梶谷真司(2018)幻冬舎
 「知の探索サロン」は、どのような場でありたいのか。身をもって考えることを学ぶ「哲学対話」を参考にしながら、サロンでの対話のあり方について共通認識を作った。自由に人に問い、人と語り合うことが広くて深い思考につながる。
「知の探索サロン」は、どのような場でありたいのか。身をもって考えることを学ぶ「哲学対話」を参考にしながら、サロンでの対話のあり方について共通認識を作った。自由に人に問い、人と語り合うことが広くて深い思考につながる。
参考図書
『江戸の読書会』
前田勉(2020)平凡社
江戸時代に行われていた読書会は、数人で同じ書物を読んで、その内容や意味を論じ合う「会読」であり、対等な立場で相互にコミュニケーションする結社であったという。読書を共通体験としながら知を探索するランダムウォーカーズが、サロンにどのように参加すればよいのかを知る道しるべとなる。
第1ユニット
コミュニケーションとキャラの深い関係
第1セッション:6月28日(金)@リクルート本社
ゲスト:京都大学教授 定延利之先生
専門は日本語を中心とした言語・コミュニケーション研究。日本語の話しことばを中心とする文法やキャラ論など、言語とコミュニケーションの研究の前提に再検討を加えている。
第2セッション:7月24日(水)@リクルート本社
第1ユニット第1セッションの振り返り(対話)
ユニットの概要
コミュニケーションに意図は必要なのだろうか。「キャラ」を手掛かりに、コミュニケーションと人間の関係への理解を深めた。人間は様々な状況に対応する中で話し方が変わるが、意図的に使い分けるスタイルと状況に応じて意図せずに変わってしまうキャラがあるという。キャラを通して私たちのコミュニケーションを顧みることで、自分と組織や他者との関係性を意識するきっかけとなった。
課題図書
『コミュニケーションと言語におけるキャラ』
定延利之(2020)三省堂
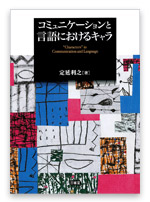
人間は変わらないということを前提にしたコミュニケーションは不自由であって難しい。しかし、本当に変わらないのだろうか。世間に溢れる「キャラ」の整理から、キャラに人間関係を調節する機能があることを教えてくれる。
参考図書
『やわらかい文法』
定延利之(2024)教養検定会議
学術書である『コミュニケーションと言語におけるキャラ』で示された「キャラ」の整理をわかりやすく説明してくれる新書。課題図書の理解を助けてくれる。
第2ユニット
遠州流茶道で体験する五感のコミュニケーション
第1セッション:9月26日(木)@遠州茶道宗家道場
ゲスト:遠州茶道宗家十三世家元 小堀 宗実 様
江戸初期の大名茶人である小堀遠州を流祖とする「遠州流茶道」の十三世家元。遠州流茶道は、わび・さびの精神に美しさ、明るさ、豊かさを加えて品格のある美を表現した「綺麗さび」が神髄とされ、「思いやり」や「もてなし」の心を大切にする茶道の基礎になっている。
第2セッション:10月17日(木)@リクルート本社
第2ユニット第1セッションの振り返り(対話)
ユニットの概要
コミュニケーションはどこから始まるのだろうか。「茶道」を手掛かりに、言葉だけではないコミュニケーションのあり方への理解を深めた。茶室で拝見する掛け軸やお道具、丁寧な所作で供されるお茶、一つひとつに亭主が客に想いを馳せて込めた意味があることを知ったとき、コミュニケーションは相手を想うことから始まっていることを実感した。守るものの背景を押さえて大切にしながら、新しいものも上手に取り入れていく姿勢は、現代にも通じる精神がある。
課題図書
『日本の五感―小堀遠州の美意識に学ぶ』
小堀宗実(2016)KADOKAWA
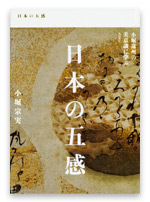
五感に響かせる総合アートディレクターとして活躍した小堀遠州が大成した「綺麗さび」とはどのようなものなのか。紹介されるお道具にあるストーリーやお家元の体験が交わることで、守るものの価値を知り、新しきを味わうことができる。
第3ユニット
私たちのコミュニケーションを守る
第1セッション:11月28日(木)@リクルート本社
ゲスト:大阪大学招聘准教授 朱喜哲先生
専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。研究活動と並行して、企業でも行動データを活用したビジネス開発に従事し、ビジネスと哲学・倫理学・社会科学分野の架橋した活動に注力。
第2セッション:1月16日(木)@リクルート本社
第3ユニット第1セッションの振り返り(対話)
ユニットの概要
コミュニケーションには、どのような言葉が必要なのだろうか。「哲学」を手掛かりに、コミュニケーションにおける言葉のあり方への理解を深めた。転ばぬ先の杖としてビジネスパーソンが哲学の言葉を学ぶことの意義を知る。また、開放的なバザールと閉鎖的なクラブの比喩を使いながら、様々な場で日常的に行われる会話の言葉遣いに着目して、私たちが言葉を介して人々とどのように付き合っていけばよいのかを考えた。
課題図書
『人類の会話のための哲学―ローティと21世紀のプラグマティズム』
朱喜哲(2024)よはく舎

自由な言葉遣いの発展のために、人類の会話を絶やさないことを哲学の任務として追求したローティが今、注目されるべき意味が書かれている。ボキャブラリーの多様性を絶やさないために、私たちができることを考えさせてくれる。
参考図書
『100分de名著 ローティ「偶然性・アイロニー・連帯」』
朱喜哲(2024)NHK出版
学術書である『人類の会話のための哲学―ローティと21世紀のプラグマティズム』で一貫して参照されているローティの哲学をわかりやすく解説した一冊であり、課題図書の理解を助けてくれる。
オプションセッション:合宿(1泊2日、日帰りも可)
都心から80分の秩父でコミュニケーションを考える
日常から離れて身体ごとランダムウォークをするために、豊かな自然と古代からの歴史を持つ秩父へ合宿に行く。秩父は主宰の梅崎先生が足しげく通う場所であり、夜祭やナイトバザールが有名で、観光やワーケーションで年間約374万人が訪れている(※)。現地に赴いて街を歩き、話を聞き、対話をすることで、その土地や建物、そこに暮らす人々との結びつきを感じながら、人が集まるコミュニケーションのデザインを考えようとした。
※秩父市「令和4年版 統計ちちぶ」8観光8-3入込観光客数より
Day1:8月24日(土)
秩父市内での町歩き@番場商店街、秩父神社など
内的なコミュニケーションのデザイン@五葉山少林禅寺
Day2:8月25日(日)
まちづくりのコミュニケーションのデザイン(人が集う場を作る)@みなのLABO
概要
<秩父市内での町歩き>
太平洋戦争の被害が少なかった秩父には古い町並みが残っており、それを活かした商店街が軒を連ねて、地元の名産品などが販売されている。秩父銘仙の歴史や秩父夜祭の由来を聞きながら町歩きをすると、秩父がもっと面白くなる。
<内的なコミュニケーションのデザイン>
五葉山少林禅寺住職 井上圭宗 様
座禅では、自分自身と向き合うだけではなく、自然の中の自分を意識させてくれる。警策は、眠気を覚まして姿勢を正すだけでなく、自分自身の内面と自分を形作る世界との関係を瞑想することを促してくれた。
<懇親会>
時間を気にせずに懇親会ができるのも、また、合宿の隠れた目的。
坂野商店(ホルモン焼き)
秩父のホルモン焼きは、昭和30年頃にダム建設のために大阪から来た工事関係者がホルモン焼き屋を開業して以来、秩父の食文化として定着したという(諸説あり)。新鮮なホルモンを使っているので臭みがなく、炭火で焼けば食感も味も抜群。町歩きで見つけた秩父の魅力を肴に、お酒も会話も弾む。
ハイランダーイン秩父(英国風パブ)
世界からも注目される個性的なジャパニーズ・ウイスキー「イチローズモルト」を、古民家を改装したレトロな雰囲気のブリティッシュ・パブでいただく。畳のお座敷席でお酒を含めば、会話も自然と和やかになる。
<まちづくりのコミュニケーションのデザイン>
みやのかわ商店街振興組合 島田憲一 様
国道を歩行者天国にして開催される「みやのかわナイトバザール」の取り組みがどのように生まれて発展したのか。人が集う場を作るという本気の想いを抱いて行動し、よりよい場を作ろうと周囲を巻き込んで試行錯誤し続けなければ、人が集う場であり続けることは難しい。人が集う場を実践し続けることの大切を学んだ。
<キャリアの本棚(ワークショップ)>
みなのLABO
1人1冊「キャリア」に関しておすすめする本を理由と共に紹介して、「みなのLABO」に寄贈する。紹介される本それぞれに、紹介者のキャリアを彩る物語があり、読書の幅を広げる刺激になる。
参考図書
『禅問答入門』石井清純(2010)KADOKAWA
『ありがとう すみません お元気で』河野太通(2017)あさ出版
『集まる場所が必要だ―孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学』エリック・クリネンバーグ(著)藤原朝子(翻訳)(2021)英治出版
班活動〜「私の知的ランダムウォーク」制作
実践者へのインタビュー:私の知的ランダムウォーク
概要
様々な世界で独自のポジションを作っている人は、きっと独自の知的ランダムウォークを実践して、そこに至っている。私たちのランダムウォークを充実させるためのヒントを求めて、私たちは、複数の班に分かれてインタビューイーを探してアポイントメントをとり、可能な範囲で同行できるメンバーと共にインタビューを行った。
課題図書
『インタビュー術!』
永江朗(2002)講談社

ビジネスシーンにおいて、インタビューをする機会はなかなかない。その「いろは」を知るための課題図書。インタビューの主役である話し手の言葉を引き出すための事前準備は欠かせない。
総復習セッション
私たちのランダムウォーク
2月20日(木)@リクルート本社

概要
私たちは1年間のランダムウォークから過剰な一歩を踏み出して、出会った未知や未踏から多くをインプットした。それらから得た気づきや想いはアウトプットとして整理することで、私たちの既知の領域が広がる。
そこで、知の探索サロンでの体験から、各々が自分の感性で広げた1年間のランダムウォークの軌跡を写真や図表を交えたA41枚のスライドにまとめて、それをA1(A4の8倍)の大きさに拡大印刷したポスターを使って共有した。共通の体験やキーワードがあるので、初めて見るポスターでも、写真や図表をきっかけに話題が尽きない。サロンメンバーとの対話によって、自分にとっての1年間の体験の意味が、広がりと深まりを帯びていった。
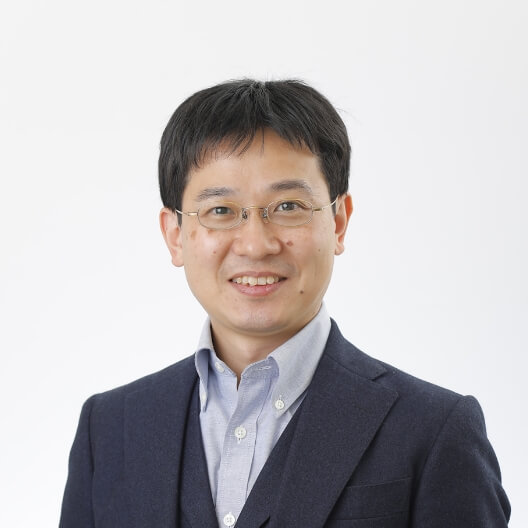
橋本 賢二
2007年人事院採用。国家公務員採用試験や人事院勧告に関する施策などの担当を経て、2015年から2018年まで経済産業省にて人生100年時代の社会人基礎力の作成、キャリア教育や働き方改革の推進などに関する施策などを担当。2018年から人事院にて国家公務員全体の採用に関する施策の企画・実施を担当。2022年11月より現職。
2022年3月法政大学大学院キャリアデザイン学研究科修了。修士(キャリアデザイン学)


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

