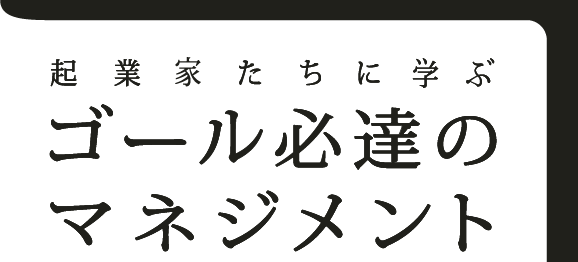
VOL.2 雇用区分パラダイムからの脱却
社員もインターンも中も外も、すべての垣根を越えて力を最大化する組織づくり

Section1 社員と学生インターン。その差は先入観がつくるだけ
「インターン募集」一般的に企業がそう広報する場合、対象はあくまで「お客さん」としての学生であることがほとんどだ。自社の業務についてアウトラインを学んでもらうため、あるいは事業のコアとなる精神を知ってもらうため、インターンのためだけのプログラムを企画して就職活動中の学生を迎え入れる。しかしここに、社員とまったく同等の業務を、まったく同等のコミットメントのもと、インターンたちに付与する会社がある。人材ビジネスのベンチャー、スローガン株式会社だ。
顧客に提供するサービスの質的低下など、通常であればリスクを先に考えてしまうところなのだが、それを実行してしまう思想はどこにあるのだろうか。
「大企業から起業して、『さて営業活動をしよう』といったときに、私はまったく営業ができなかったのです。大企業とスタートアップのベンチャーのプロセスの違いも大きかったでしょうし、エンジニアや企画畑を歩んできて、営業のスペシャリストではなかったことも大きかったと思います。つまり、6年弱の大企業での経験もベンチャーではゼロに近かったわけです。それならば、センスのいい学生なら私よりもうまく営業できるのではないかと思いました。『こうするといい』という要点を教えさえすれば、センスのいい人間なら任せられれば任せられるほど、ちゃんとやれるだろうという前提ですね」
「もう1つ想いがあります。高校の2つ先輩でマッキンゼー出身の方が経営する会社があって、そこもまた社長である彼とインターンだけで構成されている組織でした。彼は、『学生だという言い訳はカッコわるい。学生だろうが何だろうが、18歳を超えて社会に生きていたら社会人だ』と言いました。その価値観が、私にはスッと入ってきたんです。それからずっと、『立場によって区別をしない』という考え方でやってきたということです」
つまり、人としての基礎能力という"OS"については、学生も社員も変わらない。ただ、違うのはスキルという"アプリケーション"のみ。そしてそれは、教えさえすれば必ずカバーできる。そんな基本姿勢のようだ。「教える」ということについての具体策は後述するとして、まずはそもそもの大前提である「社員との垣根のないインターンを受け入れていくこと」のメリットについて、聞いてみたい。
Section2 従業員の6割を超えるインターン数。理由は"身内化"
現在、スローガンの従業員数は32名。うち社員は12名、残りの20名は大学生インターンだ。さらに、アーリーステージのベンチャーとしてはかなり珍しく、7割を新卒入社の社員が占める。
「他社さんから『新卒だけでよくやっていけますね。うちは余裕がなくて』と、しばしば言われます。しかし、うちの場合、新卒のほぼ全員がインターン経由の入社です。半年以上つき合ったうえで『うちで活躍できる』という確信を相互に持った者しか入ってこないので、必然的にミスマッチもなく、ローパフォーマーも生まれにくい。逆に転職者のほうが、3〜4回の面接を経ても、いざ一緒に働いてみたら違和感が生まれるというケースが多いように思います」
しかし、スローガンもベンチャーとして草創期から成長ステージに移りつつある。規模拡大のなか、このシステムがどこまで通用するのだろうか?
「今のところは、このままでいけると思っています。楽天などの先輩ベンチャーを見ていると、正社員が30〜40名になるまでは、知り合いの知り合いといった、いわゆる"身内"から採用していく。気心の知れた者たちで、コアな価値観を共有して組織をつくっていくほうがいいというわけです。私どもにとって、学生を長期のインターンで受け入れるというのは、まさにこの"身内化"することだと思うんです。ですから、うちも40〜50名になるまでは、この方法でやっていこうと考えています」
話を聞いてゆくにつれ、伊藤氏の経営が成り行きや無理なオリジナリティに立脚したものではなく、実によく世の中のベストプラクティスを研究し、うまく自社風にアレンジしつつ取り入れた、 "素直かつ練られた"経営であることが見えてくる。
Section3 高品質なマニュアル化と、任せて成功させるという背反両立
スローガンが採用するインターンは、営業系とマーケティング・企画系、それにエンジニア系の職種へと配属される。その教育方法は冒頭で話してくれた「営業できなかった社長自身」に端を発しているという。
「バリバリの営業職として歩んできた人からすると、インターンに対して『なんでこんなこともできないんだ』と思うでしょう。しかし、もともと口べたで引っ込み思案のエンジニア系の私ですら、きちんとアポが取れる営業になれました。だからこそ、彼らの目線で教えられるのだと思います。具体的には、起業してまもなく、うちに営業電話をかけてくる人がたくさんいたこともカギになっています。
そのときに受けた電話で『非常にうまいな』と感じるものと、『これじゃアポは取れないだろう』と感じるものがありました。そこで、私は『なぜ、この電話は切って、この電話は会う気になったのだろう?』という要因をすべて分析して、それをベースにすべて体系化してマニュアル的なものをつくりました。営業を受ける側として、私自身が学ばせてもらったわけです。その後、インターンたちとそれをシェアしていって、それぞれの観点を加えていった結果、非常にレベルの高いマニュアルが完成したのです」
アートとしてとらえられがちな営業という仕事を、サイエンスの目で体系化していくところでもまた、理系出身らしい伊藤氏の探求心と分析力が発揮されたといえよう。しかし、問題はそのメソッドが導き出す結果だ。リアルな成果を生まないサイエンスは、ビジネスでは無意味だ。
「業種にもよりますが、一般的に言って、だいたい100回電話をかけて3〜4件のアポが取れればいいほうですよね。うちは、10回かけて3〜4件のアポ率を目指していますし、事実それぐらい取れています。もちろん、アポが取れたあとの顧客接点の場面もロールプレーイングで、かなり細かく鍛えて送り出しています」
一方で、セミナーやウェブ商品などを開発するという、ある意味、この種の企業として社運を左右しかねない企画系の業務でも、スローガンではインターンが主力として働いている。一般的な企業の場合、社員であってもキャリアを積んだ者を充てることの多い領域だ。どうしても、そこに無謀さを感じてしまう。その不信に、伊藤氏は思想だけではなく、圧倒的なファクトで答えてくれた。
「確かに、最初はとんちんかんな、ズレている企画もありました。でも、結局、社員だろうがインターンだろうが、やらせてみないとわからない。やってもらってフィードバックしていくというサイクルを、どれだけ速く多く回せるかだと思います。それで筋のいい者は、本当にすぐ活躍しはじめます。任せると、創意工夫して、私たちが考えてもみないことをどんどんやってくれます。
うちで過去最大のページビューを記録したのも、実は東大3年生のインターンが仕掛けたツイッターと連動した企画でした。事実として、そういうこともできてしまうのです」
リテラシーとして共有すべきものは、徹底的にマニュアル化して育成スピードを上げる。だが、それはけっしてファストフードのそれのように、個々の自由な創造性を縛るものではなさそうだ。むしろ、本気でここまで個人の能力を信じて任せる企業は、けっして多くないだろう。マニュアルと個の創造性。この、一見背反する二律の意味を正しく認識して両立させている企業が、どれだけあるだろうか。「昔は任せて失敗させられる余裕があったが、最近はスピードと効率を迫られて、そんな余裕がなくなった」と嘆く大企業は多い。しかし、スローガンは大企業ではない。圧倒的にスピードと効率を迫られるベンチャー企業なのだ。二律背反の両立。この問題提起は、なかなか示唆に富んでいるかもしれない。

 「Good find」は、Webのみでなくフリーペーパーでも展開されている。伊藤氏は、インターンの学生でなければ考えつかないようなアイデアが次々と生まれ、それが、商品やサービスとして実現することも少なくないと語る。
「Good find」は、Webのみでなくフリーペーパーでも展開されている。伊藤氏は、インターンの学生でなければ考えつかないようなアイデアが次々と生まれ、それが、商品やサービスとして実現することも少なくないと語る。
Section4 「辞めるなら、うちにおいで」の数で測る新時代の"安定性"
クライアントのいるビジネスにおいて、育成の点で大きな比重を占める要素に「顧客に育てられる」ということがある。その視点について、伊藤氏は「経営者に会いなさい」と常に言い続けている。
「うちで最も成長した、あるいは私が『成功事例だ』と思う者を何人か見ていると、すべてお客さまに育てられているんです。しかも、相手はベンチャーの経営者。経営者に会って、30分でも1時間でも話をすると、自分が気づいていない本質的なところを指摘されて、『もっと違う目線で考えなければいけない』とか、自分がよかれと思っていたことがまったくイケていなかったとかいうことを知るわけです。経営者は率直に指摘してくれる方が多いので、『それ、おかしいよ』と言ってくださるんですね」
「10社の担当企業があれば、何社、経営者に会えているか?もし、少なければ『伊藤を連れてくるので社長に会わせてください』と、私を使えばいい。とにかくあらゆる手段を考えて会うことです」
自ら成長機会を創出すること。では、その結果、伊藤氏が目指している人材の理想型とは、どんなものなのだろうか。
「営業に関してよく言っているのは、クライアントから『君みたいな人がほしい。君みたいな人が採用できるなら、スローガンとつき合いたい』と言ってもらえるようにしようということです。たとえば、うちを辞めると宣言したときに何社のクライアントから『うちにおいでよ』と声がかかるか。終身雇用や組織に依存することが安定を意味しない時代だとすると、会社を飛び出してフリーになったときに何人から声がかかるか、その数が個人としての安定度を示していると思うんです。そんな姿勢で、お客さまから信頼される人間になろうと、常に社内で話しています」
「場合によっては、自分が学生であることをカミングアウトしたほうが、距離がぐっと縮まることもある。そんなときは、学生の視点で情報提供をすればいい。しかし、基本的にはクライアントに対して、学生であることを最後まで言いません。『関係ありません。学生だろうが何だろうが、私は価値のある提案をしています』という姿勢で臨むべきだと思いますから」
Section5 優秀な学生を惹きつけ、コミットさせるという必須の2軸
形式的にはスローガン同様、本格的な戦力としてインターンを採用している企業もある。だが、そのほとんどがスローガンのように、思想を企業ブランドや業績など、実成果へと結びつけられていないようだ。果たして、彼らとスローガンは何が違うのか。
「確かに聞きます。『インターンを採用してみたけど、全然ダメですわ』とか(笑)。私が見る限り、問題は、『本当に優秀な学生をちゃんと受け入れているのか』『その学生たちにちゃんとコミットさせているのか』その2点だと思うんです。どちらが欠けてもダメで、いくら優秀な人が来てもコミットさせられないと宝の持ち腐れになるし、逆に意欲のない人がコミットしてもダメなんです。イケてる人がちゃんとコミットする状態をつくれば、『本当にあの人、学生なの?』というパフォーマンスを出しますよ」
とはいえ、「コミットさせる」とは、これまでの話の内容からすれば、けっして精神論として「強いる」ことではなさそうだ。尋ねてみると、伊藤氏はこう言った。
「まず、わくわくする場をいかに提供し続けるかです。尖った優秀な人材は、できあがった組織や事業に、面白みを感じない傾向があります。だから、完成していない、わくわくする場を常にどこかにつくっていく。たとえば、かつてインターンの営業メンバーはフリーマガジンの営業をやっていました。そこが登竜門になっていて、どんどん成長して別の仕事へと階段を駆け上がってゆくサイクルです。ところが、このフリーマガジンがプロダクトサイクル的に成熟してきたのです。そうすると、新規の開拓先がなかったり、あったとしても可能性が低かったりして、結果も出せず、成長もできないということになります。ですから、優秀な人を惹きつけて、彼らのコミットメントを引き出すには、完成されていない組織でプロダクトサイクルとして成長期にあるものを次々に提供して、どんどん成功体験を積ませることが重要になります」
しかし、企業規模が拡大していけば、個の力に依存するのではなく「仕組み」として成功させていく必要性が、かならず生じるのではないだろうか。
「私は、今やっている事業自体を大きくするつもりはないのです。ここはコアとして、高品質な状態で回す事業として営業します。高品質な人材が集まるためのベース事業です。拡大するなら、ここをベースに、いろいろな事業をどんどん積み重ねていけばいい。グループ経営ということかもしれませんし、社内カンパニーかもしれませんね」
Section6 インターンと社員と卒業生。すべてがつながり続ける組織
自律的に、また、場の力でストレッチされ続ける人材の集合体、スローガン。組織の理想型は、最終的にどこを目指しているのだろうか。そのヒントがホームページにあるという。
「MBAや外資コンサルなどでよく使われる『アラムナイ』という言葉で、スローガンを卒業して他企業などに行ったメンバーを紹介しているんです。ただ、コンサルなどと違うのは、それをインターンでやるということ。事実、卒業後もメンバーは緩くつながっていて、パーティーなどイベントがあるたびに集まって、近況を報告し合っています。それはつまり何を意味するか。第1に、うちに対して友好的な他社社員がたくさんいるということです。これはすごくいいネットワークだと思います。第2に、その人たちが数年後に戻ってくる可能性もあるので、有望な中途予備軍になるということです。事実、銀行に行ったアラムナイが2年後に戻ってきたという例もあります。第3に、卒業生が各業界で活躍してくれることが、スローガンの強力なブランディングになるということです」
インターンと社員。ボーダーレスの思想は、外にすら及ぶということか。
「理想を言えば、そのときの立場に関係なく、各々が勝手に『スローガンのためにやろうぜ』という動機でネットワークされている状態。いわば"スローガンファミリー"のような関係性が理想ですね」
今後、スローガンが企業として拡大成長していったとき、このボーダレスがどのような形で成果を同社と社会にもたらしてゆくのか。我々も楽しみにしつつ、見守り続けていきたい。
取材日:2011年12月22日文:飯田克彦・白石久喜写真:設楽政浩

伊藤 豊 氏
スローガン 株式会社 代表取締役社長
栃木県出身。2000年に日本IBMに入社。システムエンジニア、関連会社にて新規ビジネス企画・プロダクトマネジャーを経て、本社のマーケティング部門にてプランニングに従事。その後、ベンチャー企業の設立に携わり、マーケティング、ウェブ系プロモーションを主に担当。2005年にスローガン株式会社を設立し、代表取締役となる。


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ

