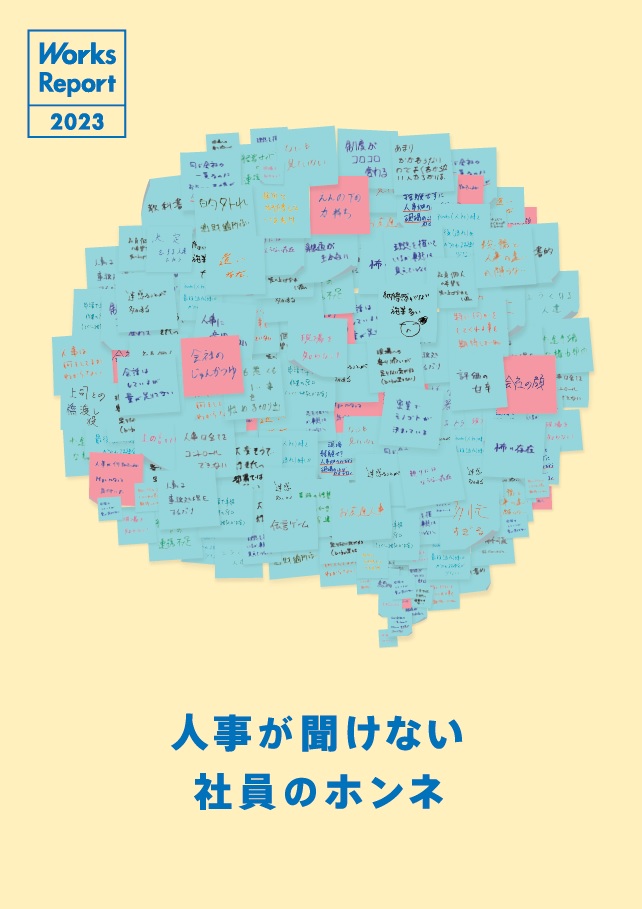演劇的手法による組織活性化のヒント(平田オリザ氏)
 劇団青年団主宰、芸術文化観光専門職大学学長 平田オリザ氏
劇団青年団主宰、芸術文化観光専門職大学学長 平田オリザ氏
相互理解だけでなく組織の活性化やイノベーションの創出を目指して、経営層と一般社員、あるいは社員同士の対話を促すことがある。だが、そうした試みがすべてうまく進んでいるわけではなく、対話の促進に悩む企業も少なからずある。そこで、長きにわたって日本の演劇界を牽引してきた劇作家・演出家であり、様々な場でコミュニケーション教育を展開してきた平田オリザ氏に、企業が対話を通じて活性化するためのヒントについて聞いた。
「他者」を交えて対話を促す
――平田さんは演劇を用いた教育活動のなかで「対話」の重要性を発信されていますが、対話とはなんでしょうか。
平田 私は対話を、「異なる価値観や文化的背景を持つ人たちとの価値観のすり合わせ」と定義しています。これに対し、同じ価値観を持つ親しい人同士でおしゃべりするのが「会話」です。また、似た言葉の「対論」(=ディベート)では、主張Aの持ち主と主張Bの持ち主が議論してAが勝つと、BはAに従います。一方、AとBという異なる主張から、Cという新しい概念を生み出そうとするのが対話です。
――演劇でも対話の手法はよく使うのでしょうか。
平田 使いますね。たとえば、家族がちゃぶ台を囲んで話すシーンのなかで、父が銀行員であることを伝えたいとします。演劇というものは不自由な表現スタイルで、テレビのように「父:銀行員」とテロップをつけることはできません。また、家族はお互いのことをよく知っていますから、妻や子どもに「お父さんの仕事って何?」というセリフをしゃべらせて説明しようとすると違和感が生じます。そこで私たち劇作家はこういう時に、他者を登場させます。たとえば、娘の恋人が初めて訪ねてくるなどの設定を用意し、彼に「お父さんはどんなお仕事をされているのですか?」と質問をさせることで、父親が銀行員であると観客に伝えるわけです。
こうして、異なる情報や価値観を持つ他者を舞台に登場させて対話を生み出し、それによって有効な情報を伝えてストーリーを展開することは、演劇ではよくあります。
――なるほど。他者の存在が対話につながるのですね。多様性や包摂性が問われる企業にとっても参考になりそうです。
平田 すべての企業にとって対話が必要かといえば、必ずしもそうではありません。たとえば、すべての社員が同じ価値観を持ち、ファミリーのように仲がいい企業が「当社はこのままでいい」と考えるなら、社内の対話を促す必要などありません。一方、「これからは多様な意見を吸い上げなければ、持続的な成長などできない」と考えるなら、企業は従来とは異なる価値観の持ち主を増やし、彼らが自由に対話できる場をつくる必要があります。
――企業が「他者」を取り込んで組織の活性化を目指す時、どう取り組めば効果が上がりやすいとお考えですか。
平田 他者が入ることで組織全体のパフォーマンスが上がったという小さな成功体験を、トップが意図的に用意するのがいいと思います。異文化をバックグラウンドに持つ人が組織に入ってくると、最初のうちは面倒なことも起こります。でも、「面倒なこともあるけど、組織に多様性があることは楽しいし、成果も上がりやすい」と多くの社員が実感できれば、企業は変わっていきます。
「フィクションの力」で意見を引き出す
――平田さんは、社員研修や管理職研修で教える機会も多いそうですね。
平田 はい。その際、経営層や管理職の人から、「若い社員が意見を言わない」とか「新人が何を考えているのかわからない」などの愚痴をよく聞きます。でもそれは、若手個人の問題ではなく、コミュニケーションのデザインが間違っているのではないかと思うのです。若い世代のコミュニケーション能力は、上の世代より劣ってなどいません。コミュニケーションのとり方が多様化しているのであって、それに応じたやり方を用意する必要があります。
若手とのコミュニケーションのとり方をもっと工夫してはいかがでしょうか。たとえば従来型の会議だけでなく、1対1、1対3くらいの小規模ミーティングや、取締役と新入社員だけの会議を開いてみる。あるいは、あえて今、居酒屋での「飲みニケーション」を試すなどです。どのやり方が誰に刺さるのかわからないので、まずはいろいろ試すことが大事です。そうやってコミュニケーションのデザインを変え、若い世代の意見を最大限引き出せるような仕組みを整えることが、管理職の役割でしょう。
――意見を引き出すためには何が大切ですか。
平田 まずはオープンマインドであることです。たとえば会社で事業について議論をする時、管理職があらかじめ「正解」を隠し持っていると、メンバーはそれを敏感に悟り、正解に近づくための議論をしてしまいます。だから管理職は、「私も答えは知らないんだよ」という態度を示さなければなりません。管理職が「正解」を用意したり議論を誘導したりするのではなく、オープンでフラットな姿勢で対話を促すべきです。そのためには、周囲とは異なる意見の持ち主を頭ごなしに否定しない、相手を役職名ではなく「さん付け」で呼ぶなどの取り組みを進め、企業全体のカルチャーを変えることも重要でしょう。
もう1つ勧めたいのが、「フィクションの力」を借りることです。たとえば、私が学長を務める大学では、受験生に6~7人のグループを組ませ、「ディスカッションドラマ(討論劇)」という試験を課しています。「日本が財政破綻してIMF(国際通貨基金)の管理下に置かれた結果、本州と四国とを結ぶ3本の橋のうち2本を廃止することになった」といった設定を与え、6~7人のうち1人が議長役を担当。残りが関係各県の知事役を演じ、自らの県に橋を残すために議論をさせるのです。こうして虚構の設定と役柄を与えると、対話に慣れていない人でも周りに流されることなく、自分の意見を堂々と言えるようになります。
――架空の設定を用意することで、対話に慣れていない社員でも、自らの考えを表現しやすくなるのですね。
平田 その通りです。フィクションの力を借りるやり方は、他にもあります。糖尿病の治療チームに対して研修を行ったときは、医師がケースワーカー、看護師が患者さん家族の役柄を演じるロールプレイをしてもらいました。こうすることで従来とは全く異なる視点に立ち、新たな気づきが生まれるなどの効果が得られます。
これからの日本は、多文化共生型の社会にならざるを得ません。既に地方では、人手不足を補うために多くの外国の方の協力が必要になっています。そうした状況に、企業も対応していく必要があります。そのためには、ロールプレイを通じて他者を理解するなどの試みがさらに重要になると考えています。
――平田さんはこれまで、外国劇団との共同公演など多くの海外プロジェクトを率いてこられました。異文化の人々と価値観をすり合わせるコツはあるのでしょうか。
平田 ひとことで言うと余裕、でしょうか。心のゆとりや時間のゆとりがないと、異文化をうまく取り入れるのは難しいと感じます。また、若い頃からいろいろな文化に触れ合う経験を持ち、異なる文化との出会いを楽しめるようになるかという点も大きいでしょう。
「スイング」を配置して組織の持続可能性を高める
――舞台には、役者さんや裏方さんなど多くの方が関わります。組織を運営するにあたって工夫されたことはありますか。
平田 コロナ禍以降、代役を用意するやり方を変えました。それまでは役者に不慮のトラブルが起きた際に備え、主役級だけに「アンダースタディ」と呼ばれる代役を用意するのが普通でした。ところがコロナ禍で公演中止が相次ぐなか、どの役柄でもこなせる「スイング」というポジションを1~2人用意するケースが増えています。スイングを用意するためには手間とコストがかかるのですが、若手の俳優にとっては成長のチャンスになりますし、劇団全体にもいい影響を及ぼします。
今後は企業でも、スイングのような存在が必要かもしれません。誰かが出産・育児や介護で一時的に仕事から離れなければならなくなった時、その人の仕事をすぐに担当できる人を用意しておくわけです。
――組織のなかに、バッファーを用意するのですね。
平田 そうです。生態学者・民族学者で思想家の梅棹忠夫先生が「請われれば一差し舞える人となれ」とおっしゃっていましたが、まさにこれがスイングです。リーダーシップではなく、フォロワーシップを発揮するポジションです。こういう役割の人を置いて組織にゆとりをもたらし、企業の持続可能性を高めたり社員の生活の充実を目指したりすることは、企業トップの重要な役割なのではないでしょうか。
――スイングのような役割は、誰にでもこなせるわけではない気がします。
平田 おっしゃる通りですね。経験豊かなベテランに任せるのは、有力なやり方だと思います。一方、若手をこうしたポジションに置き、幅広い仕事を見聞きさせるのも1つの手です。
――演劇で取り入れられている手法は、企業にもたくさんのヒントがありそうです。
平田 香川県小豆島(しょうどしま)に、役者から裏方までのすべてを地元住民が担う「農村歌舞伎」というものがあります。これに代表されるように、演劇は昔から、地域の共同体を維持する役割を果たしています。演劇から共同体の運営方法を無意識に取り入れているところがあります。
演劇が生まれてから約2500年たったといわれています。その間、演劇人は脚本・演出・演技といった各分野で、どうすればコミュニケーションがうまくいくのか追求してきました。そうしたノウハウが、今後の学校教育や、企業内のコミュニケーション教育に役立つと私は考えています。
聞き手:橋本賢二(研究員)
執筆:白谷輝英


 メールマガジン登録
メールマガジン登録 各種お問い合わせ
各種お問い合わせ